|
~ プロローグ ~ |
|
ざあざあと、寄せては返す波の音を聞きながら、あなた達はベレニーチェ海岸を歩いていた。 |
|
~ 解説 ~ |
|
二人で落とし穴に落ちました。 |

|
~ ゲームマスターより ~ |
|
ゆるっとしたエピですので、どうぞゆるっとお楽しみください。 |

|
◇◆◇ アクションプラン ◇◆◇ |
|
||||||||
 |
ヨナが穴に引っかかり掴んだベルトルドを道連れ 「…な、なんでベルトルドさんまで落ちてるんですか」 なんでもなにもお前が掴んだからだ 「持ち前の運動能力はどこへ?二人とも落ちたら出られないじゃないですか」 あのなぁ…(渋い顔 「困りましたね」 確か背中側のウエストポーチに信号拳銃があった筈だ。それで助けを呼ぶ 取れるか? 「待ってください。暗いし狭くて…」 ごそごそ …っ 「? …あっ。すみません」 「ベルトルドさん、やっぱり猫っぽい所あるんですね…」 猫ではない。が今はどうでも良いので早く信号弾を 「分かってます、すぐ取りますから」 ……っおい 「わ、私だって触りたくて触ってる訳じゃないです」 視点 ベルトルドからヨナにシフト |
|||||||
|
||||||||
 |
今朝早く起きたせいでいかにも眠そうなレオノルを連れて砂浜を歩いているとき 穴に落ちかけたレオノルを救おうとしショーンも一緒に落とし穴へ 彼女を下敷きにする訳にもいかず、彼は身をよじってレオノルの下敷きに (ドクターは今俺が受けたダメージも計算できるんだろうな)と余計なことをショーンは思う一方、「出して」と喚くレオノル 貴女が上に乗っているから私は助けようもないんです、とりあえず落ち着いてと彼は返すが、彼女はうとうとしだした しばらくするとレオノルはショーンの胸に頭を乗せ、寝息を立てて眠り出した 早く脱出したいのだがと思いつつ、熟睡していて起こすのも可哀想なので彼女の身体が冷えないようにと彼はそっと寄り添う |
|||||||
|
||||||||
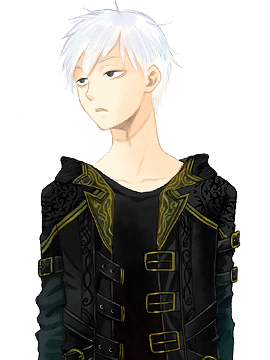 |
(一応脱出しようとした後) 疲れた。もう動きたくない。酒飲みたい 足ものばせないし、ルドはゼロ距離で近いし、なんかいい匂いするしやだもう 女の子のシャンプーみたいなにおいする (じっとりと嫌そうにルドを見る) (暗いのにそれだけ近くにいるってことだ) (呼吸までわかる) ルド、俺さ キスしたことないんだ 女の子と手握ったこともないし、見つめ合ったこともないし、好き合ったこともない どういう気持ちなんだろうなぁ いいなぁ俺もいつか好きになって、好きになってくれる人がいればいいなぁ え?試す?何を ……!!!! ちょ、ちょっと待って! (脱兎の如く離れる) こ、こういうのは、好きになってからだろ! (動悸が止まらない) あほ、ばか |
|||||||
|
||||||||
 |
グレン大丈夫ですか! 思いっきり下敷きにしちゃったんですけど! 早くここを出な…ああっ、砂が沢山落ちてきますぅぅぅ! せっかくなので星の話でもしましょうか。 この穴が大きければもっと星が見えたんでしょうけど…残念です。 一方的に私が喋ってるだけですけれど、グレンが時折相槌を打ってくれるだけでも何だか安心しますね。 ふと思ったのですが。 今までここまでグレンの近くでお話するようなことってありましたっけ? ないですよね? グレンの顔を見ていたら何だか恥ずかしくなってきた、ような。 咄嗟にグレンにくっついて顔を隠します。 あっ、はい、そうです少し眠気が。 …そういうことにしておきます。 あ、撫でてくれてる…気持ちいい、な。 |
|||||||
|
||||||||
 |
【目的】 (くそっ! ミニュイと向かい合った途端に落ちるとか、コメディかよ!) って、嘆いている場合じゃねぇか。 空を見上げながらも、右の腰に差したスコップ(小)を抜く。 時間の無駄だ、ここから抜ける。 【会話】 ショウ :……今回は、足場も悪いようだな。 (それまでうつ伏せだった体を肘まで起こす為、左手をついたが、 手の感触に違和感がよぎる) ミニュイ:感触は、どう? ショウ :(違和感を無視し、砂で作られた壁を右手でつかみ取る。 質感によっては、スコップ(小)で掘り、登る足場を作る為) (砂の質を見ながら)意外とあるな……あっさり零れちまった。 ミニュイ:そりゃあそうよ、巻いてないもの。 ショウ :本当巻いていな、……巻く? |
|||||||
|
||||||||
 |
◆アユカ 突然落下したかと思うと、目の前にかーくんの顔があって 彼の上に覆い被さってるみたいで…!? 慌てて離れる 一体ここ、どこなの!? かーくんに宥められて深呼吸 …ごめんね、取り乱して その、落ちた拍子にいろいろ触ったり触られたりしてないかな、って… だ、大丈夫、たぶん触られてないし! だから気にしないで…! ◆楓 突然落下したかと思うと、アユカさんが覆い被さっていて… などと思う前にパニック状態の彼女を落ち着かせる 落とし穴か…まあ、出る手立てはあるでしょう それにしても、いつになく慌ててどうしたのですか 彼女の言葉に一瞬思考が固まる もしかしてその…妙な所に触れてしまったでしょうか だとしたら、なんと詫びればいいか… |
|||||||
|
||||||||
 |
え、なに?落ちた…? …え!? 急な事に咄嗟に反応できず状況整理しているうちに呻き声聞こえびっくり あっ、セシルくんそこ!?ごめんなさい、大丈夫!? ……今、重いって言いかけなかった? ま、まあ今は追及している場合じゃないわよね これ、落とし穴よね? 私達だけで出るのは難しそうかしら… いえ、気にしないで 私もさっき思いきりのしかかっちゃったし …筋力の問題なのかしら 密着しちゃうとか、もっと別の気にするべき所があるような そういえば水着来た時も無反応だったなあと とりあえず聞くわ ちょっと予想がついている 全部じゃないわね、一部ね 本当に隙あらば要求してくるわね… まあ今回は理由が正当だし… ようやく笑った相方に なんだか複雑… |
|||||||
|
||||||||
 |
エリィ 落ちましたカ… ハイ、レイさんが庇ってくれたので平気デス 夜の海が危険だと言っていた意味がよく分かりまシタ (レイさんだし紳士だし、異性として意識していないので油断していたが 触れられた感触に、びくっと反応してしまう) イエ、ナンデモナイデス!大丈夫デス!! (他意はないのデス。…少しくらい我慢しまショウ) あ…やっぱり待ってくだサイ…そこは! …ふはっ、アハハハハハハ!!! く、くすぐったいのでっ、ソコは触っちゃダメデスーっ! うぅ、ひどいデス…笑いすぎて腹筋が痛いデス… ふふっ いえ、ただ…レイさんがこんなに楽しそうなのは初めてだったので 嬉しくなってしまいまシタ えっまだくすぐる気デスカ?! 勘弁してくだサイ! |
|||||||
|
~ リザルトノベル ~ |
|
●闇の中、ともにいるのは異性のあなた 落ちる! と思ったときには、すでに遅し。 ヨナ・ミューエは、穴の中へと滑り落ちていた。 「ああ……」 暗い穴の底で、悲嘆の声を漏らす。 砂に囲まれた中は、暑さの名残が残っている上に、狭い。 さらに言えば、壁の終わりは、ヨナの身長よりもはるか上である。 そして、一番悪いことは――。 「……な、なんでベルトルドさんまで落ちてるんですか」 抱き着かんばかりの近い距離。正面に、ベルトルド・レーヴェの存在があることだった。 ベルトルドは、座ったまま、ヨナに恨めし気な目を向けた。 「なんでもなにもお前が掴んだからだ」 そう言って、自身の腰の辺りに視線を落とす。 そこにあるのは、ベルトルドの団服の裾を掴む、小さな手。 「あっ……」 ヨナは慌てた様子で、手を引いた。その顔が、気まずそうに歪む。 だが、それは一瞬だけのこと。彼女はすぐに、いつものクールな表情に戻った。そして口から出た言葉が、これだ。 「持ち前の運動能力はどこへ? 二人とも落ちたら出られないじゃないですか」 「あのなぁ……」 ベルトルドは嘆息した。 だが、お前のせいでと言ったところで、状況は変わらない。 それにベルトルドはさきほど「やってしまった!」とでもいうようなヨナの表情を見ている。その後、彼女の口からさらりと言葉が飛び出したのは、きっと己の失態が情けないのもあるのだろう。 と、思えば。 「困りましたね」 穴を見上げるヨナに、これ以上何かを言うことはあるまい。 「確か背中側のウエストポーチに信号拳銃があった筈だ。それで助けを呼ぶ。……取れるか?」 ベルトルドは、膝立ちになり、ヨナを見下ろした。座ったままでは、壁に押し当てられているポーチは、開けられない。かといってここで立ち上がり、ヨナに背を向けるだけのスペースはなかった。 「待ってください。暗いし狭くて……」 ヨナが正面から、ベルトルドの腰に手を回す。まるで抱きしめるような仕種だが、真剣なヨナは気づかない。ベルトルドも、特に何も言わなかった。 ――ただ。 「……っ!」 彼女の手が、尻尾の付け根に触れたとき。 ベルトルドの尾が、ビクッと跳ねた。 ヨナの手の動きが止まる。 「……あっ。すみません。……ベルトルドさん、やっぱり猫っぽい所があるんですね……」 (……猫ではないんだが) ベルトルドは内心でため息をついた。 だが、今はそんなことを言っている場合ではない。 ヨナがこの体勢を意識したら、どんな反応を見せるかわからない。 早々に、必要なものを取り出してもらわねば困るのだ。 「早く信号弾を」 あえて短く言って行動をせかせば、ヨナはちろと、ベルトルドの顔を見た。 「分かってます、すぐ取りますから」 小さく滑らかな手が、再びポーチを求めて動き出す。 が、尻尾を避けようとしているからか、それはベルドルドの背中の方へと進んでいった。 触られて困るものではないが、この状況では、いかにせん。 「……おい」 「わ、私だって触りたくて触ってる訳じゃないです。ただ、よく見えないからっ……」 ヨナは、不機嫌に唇を尖らせた。 それに、この筋肉質な体に触れ、尻尾の反応を見ていると、なんだか気持ちがもやもやしてくる。 (……ベルトルドさんは、異種族の異性なんだって思い出したというか……) そんな当たり前のことを、なぜ今更。自ら突っ込みつつ、ヨナは、ポーチの中に手をやった。 と、見つけた信号弾を取り出す際に、その端がまた偶然、ベルドルドの尾に触れた。 黒く柔らかなそれが、再びピクリ、跳ね上がる。 (……触られるのは意外と駄目?) だとしたら――。 (私ばっかり、恥ずかしいところを見られずにすむかもしれません) ※ 信号弾は、穴の底から星空へと、まっすぐに上っていった。 「これで誰かが気づくだろう」 狭く切り取られた夜闇を見上げ、ベルトルドが呟く。 「じゃあ、それまでの辛抱ですね」 言いながら、ヨナは彼の胸板に右手を伸ばした。 (触られるのが得意じゃないなら、きっとびっくりするはずです) 指を広げた手のひらで、分厚い筋肉をそうっと撫ぜようとする――と。 「そういう事をする相手は選べ」 ベルトルドが、ヨナの手首を掴みとった。 大きな手だが、彼は、大して力を入れている風には見えず、ヨナの手首にも痛みはない。 にもかかわらず。 ヨナが、開いていた手でこぶしを握り、力を入れても、彼の腕は、微動だにしなかった。 「ヨナ?」 声と共に、ベルトルドがヨナの手首を離す。 が、ヨナは彼と視線を合わせられない。 唐突に、理解したのだ。 (ベルトルドさんが男性って、こういうこと、なんですよね……) 体のつくりも、力の強さも、まるで違う。 彼はヨナの動きを、腕一本で封じることすらできるのだ。 意識すると、急に胸の奥が、ざわつき始めた。 ただそれがなぜなのかは、ヨナにはわからなかった。 ●あなたは星だけ見ていればいい 月と星が輝くベレニーチェ海岸を、ショーン・ハイドは歩いていた。 傍らには、ふあ、とあくびをしているレオノル・ベリエ。 「ずいぶん眠そうですね。出歩くのはやめておいた方が良かったですか」 ショーンが言うと、レオノルはぱちりと目を瞬き、ショーンを見上げた。 「ん~、今朝早かったからね。でも大丈夫」 涙の浮かんだ目をごしごしと擦りながら、そんなことを言う。 (とはいっても……さっさと見て回って、早めに帰寮するか……) ショーンがそう思ったとき。 「うわっ!」 突然、レオノルの体が前方へ傾いた。 「ドクター!」 すぐさま伸ばした腕を、レオノルの腰に回す。が、引き寄せるには、バランスとタイミングが悪かった。 「くっ……」 ショーンは、彼女を抱えたまま、穴の中へと落ちていった。それでも咄嗟に、身をよじり、レオノルを抱きとめる姿勢をとる。 その数秒後、背中に痛みが走った。 「うっ……」 細く小柄なレオノルとはいえ、抱えて落ちれば、それなりの衝撃だ。 思わず呻くと、腕の中の存在がもぞりと動く。 「ショーン!」 レオノルは、ショーンの胸に置いた手で、体を支えるようにして、身を起こした。 (ドクターは今俺が受けたダメージも計算できるんだろうな) こんなことは、今考えるべきことではないはず。それでも頭に浮かんでしまったのは、ショーンもそれなりに、動揺しているということだろう。 「頭は打ってないよね? 体は動く?」 レオノルはもぞもぞと動き回り、ショーンの腕を持ち上げ、膝を曲げさせた。 「痛みはない? そう、……なら大丈夫だね。おそらくこの穴の深さは、ショーンの身長程度。よほどのことがない限り、大事には至らないはずだし」 そう言ってはみたが、レオノルにとって、穴はかなり高い位置にあるように見えた。 切り取られた空に、星が見えたからかもしれない。 「ショーン、平気ならすぐにでもここから出よう! 出たい!」 レオノルは、ショーンの体から降りようと、もぞもぞ動き始めた。 「ドクターとりあえず落ち着いてください! そんなに動かれると少しくすぐったいです!」 ショーンが、レオノルの両腕を掴む。 レオノルは不満顔で、ショーンを見下ろした。 「私は落ち着いてるよ! でもどうやって穴から出ればいいのさ!?」 「それは……」 「ここを上れと言われても、私には無理だよ」 ショーンはすぐ近く、砂の壁に手をやった。海岸の砂はさらさらと、手のひらの中へこぼれ落ちてくる。たしかにこれでは、ショーンでも上るのは難しいだろう。 「ほら、考えて」 「……ドクター」 (それはあなたの仕事ではないのか) 一瞬ちらり、ショーンは思った。 が、言っても無駄とはわかっている。なにせレオノルの得意は研究分野。彼女も承知しているから、ショーンの上で、「ほら早く」と動いているのだ。 「貴女が上に乗っているから私は助けようもないんです、とにかく静かにしていてください」 (そんなこと言われたって……) レオノルは、きょろきょろと周囲を見回した。 そこにあるのは砂の壁。なにか興味を惹かれるものがあればいいが、そんなものは見えやしない。 と、ショーンが仰向けに寝転んだまま、はるか頭上を指さした。 「ドクター、あそこに星が見えるでしょう」 「……見えるね。この時期、この場所、この時刻ならばおそらく――」 レオノルが語り始める。しかしそれを、ショーンが遮った。 「それなら、天体の軌道計算でもしててください」 「軌道計算?」 レオノルの瞳が、それこそ星のごとく、きらりと輝く。 黙り込んだレオノルを見て。 (突っ込まれると思ったのに実際にやり始めたなこの人) ショーンは細く息を吐いた。レオノルには、それだけの知識や計算能力もある。 (……だが、俺の方はどうするか) 砂壁は上っていけそうにないし、そもそもこの体勢を何とかしないことには、動くに動けない。 (とりあえずドクターを抱き上げて、二人で立つくらいのスペースならあるか……。ああでも、計算を邪魔してしまうのは悪いか?) そう考えたところで。 空を見上げていたレオノルが、急にくたりとうつむいた。 「……ドクター?」 名を呼ぶも、彼女は、ショーンの胸の上に倒れ込んでくる。 「ドクター!」 もしや体調でも悪くなったのか。そんな不安とともに顔を覗けば、唇からは、すうすうと、子供のように健やかな寝息が。 「……早く脱出したいのだが」 そう言えばあくびをしていたなと思いつつ、ショーンはレオノルの細い肩を、抱き寄せる。 季節は夏とはいえ、今は夜。体を冷やしてはいけない。 (寝不足ならば、起こすのも気の毒だしな) レオノルの適度な重みを胸に受け止め、ショーンはぼんやりと、空を見上げる。 丸い空には、先ほどレオノルが見上げていただろう星が、きらきらと輝いていた。 ●閉ざした逃げ道、進む覚悟はいまだなし 「疲れた。もう動きたくない。酒飲みたい」 アシエト・ラヴは、落とし穴の底で、膝を立てて座り込んでいた。 「足ものばせないし、ルドはゼロ距離で近いし、なんかいい匂いするしやだもう」 そう言って、つんと唇を尖らせる。 「いい匂い……?」 ルドハイド・ラーマは首を傾げた。 何度か壁を上ろうとしたお蔭で、足元には崩れた砂がたまっているし、さらには、男二人、実りのない行為で汗をかいている。 つまり、いい匂いの要素が何もない。その上、その香りは、ルドハイドの鼻には届いていなかった。 (……それが、俺の香水の匂いでないことを祈る) 細く息を吐き、ルドハイドは、正面のアシエトを見やる。 二人は今、互いに開いた足の間に、各々の片脚を入れることで、なんとか地面に座っていた。それはつまり、この穴の底はそれほど狭い、ということだ。 「俺もできればお前から一刻も早く離れたいがそうもいかない。助けが来るまであきらめて、せめて、静かにしろ」 言われ、うつむいていたアシエトが、頭を上げた。 ルドハイドがこちらを見る顔は、まるで駄々をこねる子供を見るような表情。 (ったく、嫌なのはお互い様だろ) 本当ならば、そう口にしてやりたいところだ。だが下手に何か言えば、嫌味が返ってくることは経験済みである。 だからアシエトは、ただルドハイドを、睨みつけるにとどめた。 喋らぬ二人、穴の中には、ただ静寂が満ちている。 いや、耳をすませば、遠く波の音も聞こえるか。 (ってこれは……ルドの呼吸の音か?) ルドハイドは、ぼんやりと頭上を見上げていた。 (この闇で、顔が見えて、呼吸の音まで聞こえるっていうのは、それほど近くにいるってことだ……) だからどう、ということはない。 だが、気づけば。 ルドハイドのすらりとした首筋を眺めつつ、アシエトは、口を動かしていた。 「ルド、俺さ。キスしたことないんだ。女の子と手握ったこともないし、見つめ合ったこともないし、好き合ったこともない」 静かになったと思っていたアシエトの、いきなりな言葉に、ルドハイドは、目を見開いた。 (なぜ突然こんな話題を?) さらには「その年でか」と言いそうになるが、それは慌てて飲み込んだ。かわりに視線が、アシエトを向く。 (知ってる、こいつは壊滅的に女にモテない) 問題は、野暮ったい髪型か、それともやる気のなさげな眼差しか。 (いや、酒のみでひねくれ者で、子供っぽいところか……?) およそ声に出しては言えない言葉が、ルドハイドの脳内に、浮かんでは消えていく。 ただそれは、アシエトのあずかり知らぬこと。 「どういう気持ちなんだろうなぁ……」 ぼんやりと、アシエトは呟いた。 「いいなぁ俺もいつか好きになって、好きになってくれる人がいればいいなぁ」 ――そのとき。 アシエトがルドハイドを見たのは、ただ彼が、目の前にいたからに過ぎないはず。 それなのに。 「……試してみるか?」 ルドハイドはそう言って、砂の壁にもたれていた背を起こした。 「試す? 何を」 聞くも、彼は無言。 腰を上げ、前傾姿勢になったルドハイドの右手が、ゆらり。アシエトに向けて、伸びてくる。 指先が触れるのは、アシエトの顎の先。 ルドハイドの細い首筋が、そして、いつも辛辣な言葉を紡ぐ唇が、ゆっくりと近付いてくる――。 (えっ、これって……!) 「ちょ、ちょっと待って!」 目を見開き、アシエトは、ルドハイドの肩を押し返した。 ここがもっと広い場所であれば、それこそ脱兎のごとく、逃げたいところ。 だが背は当初から、砂の壁についている。だから、思い切り叫んだ。 「こ、こういうのは、好きになってからだろ!」 相手は嫌味なルドハイド。わかっているのに、心臓が、全速失踪したみたいに鳴っていた。 「なんだよこれ、ルドのあほ、ばか」 腰をよじって砂の壁に向かい、ただひたすらに、小声で悪態を繰り返す。 そうでもしなければ、この動悸はおさまりそうにない。いや、そもそもどきどきしたことなんて、信じたくもなかった。 「すまない、からかい過ぎた」 小さな体でもないのに、小さく丸まったアシエトの背を見やり、ルドハイドは呟いた。 もてないから、経験なんてないだろうとは思っていたが。 好きでもない男にからかわれただけで、こんな反応を見せるというのは、想定外だ。 (ここまで純粋とは……子供みたいだな) 驚き半分、呆れ半分。ルドハイドは、アシエトの頭に手を置いた。 ぼさぼさの髪をくしゃりと混ぜれば「なんだよ」と声が。 「いや、このくらいがちょうどいいのかと思ってな」 「……ガキ扱いするな!」 アシエトが振り返る。顔は赤く染まっていたが、闇が、その色を隠していた。 ●星下に眠る少女を抱く まるで穴に飛び込むように、思い切りよく落ちたにもかかわらず。 ニーナ・ルアルディを襲う衝撃は、想像よりもずっと小さなものだった。 ニーナの下には、グレン・ガーヴェルが横たわってのだ。 「グレン大丈夫ですか! 思いっきり下敷きにしちゃったんですけど!」 仰向けのグレンの、腰の辺りをまたいだ姿勢で、ニーナは彼の顔を覗き込んだ。 もし大変なことになっていたらどうしようと、そうっと手を握る。 だがグレンは、ニーナをみるとにやりと笑った。 「……今も下敷きに、しちゃってる、よな」 グレンにしてみれば、正直笑うどころではない。 うちつけた体はジンと痛いし、顔には一緒に落ちてきた砂がかかっていた。 ただ、ニーナが心配そうな顔をするから、軽口を叩いたのだ。 「ごめんなさい、あのっ」 「いや、大丈夫だ。俺が起きないと、下りるスペースもないだろ?」 「そう、そうなんです!」 ニーナは深くうなずき、開いた手を、砂の壁に押し当てた。 「だから、早くここを出な……」 言うなり壁を掴み、上ろうとするのだが。 「……ああっ、砂が沢山落ちてきますぅぅぅ!」 「ぷへ、ああ、そうだなっ……けほっ」 顔面に降ってきた砂に、グレンは思い切り咳き込んだ。 砂浜の砂はさらさらと柔らかい。そう簡単に上れるはずがないのである。 「お、落ち着けって!」 ぶるぶると顔を振って砂を払いのけ、グレンはニーナのウエストに、手を添えた。 「暗いし、下手に動くと事態の悪化を招きかねねぇ」 「で、でもっ……グレンが……痛い、ですよね……?」 「俺?」 こくこくと、ニーナがうなずく。さっきのグレンの笑顔が、無理をしたものだと気づいているのか。 (ったく普段は鈍感なくせに) 「俺なら大丈夫だから……じっとしてろ。朝には誰かしら迎えに来るだろ」 そして今。 壁に背をつけ胡坐をかいたグレンの膝の上に、ニーナがちょこんと座っている。 ニーナは辞退したのだが、これがいいと、グレンが主張したのだ。 「……せっかくなので星の話でもしましょうか」 ニーナは、さきほどよりはだいぶ落ち着いた様子で、頭上を見上げた。 そこには、丸く切り取られた空がある。 「この穴が大きければもっと星が見えたんでしょうけど……残念です」 そう言った彼女は、今までに読んできた本に書かれていた、様々な星の話を始めた。 少女の声が、高く細く、夜闇に響く。 それを聞きながら、グレンは、ニーナをそっと抱きしめた。 平気な風を見せているが、ニーナがこうしてしゃべり続けているのは、不安な証拠。 昔からの癖なのだ。 (だったら……。俺は星にあまり興味はないが、これでこいつの気が紛れるなら聞いてやろう。こうしてくっついていれば、夜風に冷えることもないはずだ) ニーナは思いつくまま、話を続けていた。 グレンは、多くは語らない。 (でも時折相槌を打ってくれるだけでもなんだか安心しますね) 聞いてくれる人がいる。感じられる温もりがある。 だからこそニーナは、この狭くて暗い穴の中でも、なんとか騒がずにいられるのだ。 ――と。 「ここまでグレンの近くでお話するようなことってありましたっけ?」 ニーナは、グレンを振り返った。 「ないですよね?」 聞いたことに、深い意味はない。 でも振り返って初めて。 「そうだったか?」 そう言うグレンの顔が、とても近いことに、気がついた。 見られることが、見つめることが、恥ずかしくて。 (だめっ……) ニーナは咄嗟に身をよじり、グレンの胸に頬を押しつけた。 「どうした、眠くなったか?」 「あっ、はい、そうです少し眠気が」 早口で答えて、ぎゅっと目を閉じる。 (……そういうことにしておきます。恥ずかしいなんて、言えるはずがありませんから) 「確かにここに落ちてから大分経ったからな、無理もない」 グレンは、赤ん坊にするように、ニーナの肩を、とんとんと叩いた。 「俺は朝まで起きてるつもりだから、お前は安心して寝とけ」 「えっ、でも、それじゃグレンが……」 困惑した声が聞こえるが、それには「馬鹿」と返す。 「俺まで寝たら護衛になんねーだろ。ほら、もっと寄りかかっていいから」 グレンの大きな手のひらが、静かに優しく、ニーナの長い髪を撫ぜる。 (……気持ちいい、な) 抱きしめられた背中の温もりと、手の感触に包まれて。 ニーナはうっとりと目を閉じた。 聞こえてきた寝息に、グレンがほっと息を吐く。 「寝てくれてよかった。この距離でいつも通り話し続けるのは流石にキツイ」 呟き、起こさぬように気をつけて、グレンはニーナの寝顔を覗き込んだ。 ふっくらとした頬と、桃色の唇は、あどけない。 「……ホント無防備で、無邪気で……」 ――だから、放っておけない。 グレンは、星空を見上げた。ここに朝日が見えるのは、あと何時間後だろうか。 ●闇に隠れた大人の遊戯 「あーっ、くそっ!」 狭い狭い、穴の底。 ショウ・イズミは、砂の上にうつ伏せになったまま、顔だけを持ち上げた。 (落ちたっ、思いっきり!) 口の中に入った砂を吐きだし、周囲を見やる。 が、前も左も右側も、見える範囲は全部が黒い。闇色だ。 「こんなところに、くだらないもの掘りやがって」 子供の悪戯にしては穴が深すぎるし、大人がやったなら許しがたい。 ショウはどん、と砂の壁を殴りつけた。 とたん。 「うわっ」 上から砂が零れてきて、慌てて目を閉じる。 幼い頃から教団の寮で暮らしてきたショウは、エクソシストたちが仲間と賑やかに騒ぐ姿を見て育った。 自分はその輪に入ることは苦手でも、それなりに、宴会的なノリも知っている、が。 「こんなの、罰ゲームでも見たことないぞ!」 はあっと深く息を吐き、汚れることを承知で、顎を置いた。 首だけを上げているのは、なかなかきついのだ。 (……しかもミニュイと向かいあったとたんに落ちるとか、コメディかよ!) なんとなくやわらかい感触のする場所に、顎の先をぐりぐりと押しつける。 これもすべて、不機嫌ゆえの行動だ。 だが、ふと――。 (そういえば、ミニュイはどこだ?) パートナー、ミニュイ・メザノッテの顔が見えないことに、気がついた。 でも確かに一緒に落ちたはずだから、この狭い穴のどこかにはいるのだろう。 「おい、平気か?」 ショウは声を張り上げた。起き上がり探すよりも手間が省けると思ってのこと。 案の定、どこからか、落ち着いた声が聞こえる。 「大丈夫よ。ショウは……怪我はないようね」 「ああ」 ショウは、起き上がるべく、自身が倒れていた下に左手をついた。 と、開いた手指に間に、むにり、とした感触。 「……今回は、足場も悪いようだな」 言いながら、砂浜とはいえ、土はこれほどに柔らかなものだっただろうか、と思う。 (湿っている……わけでもないしな) しかしとりあえず、起き上がらないことにはどうにもならない。 ショウは手に力を込めて、上半身をずいと持ち上げた。 なにかをむちりとつぶした気がするが、きっと海藻でも落ちていたのだろう。 「時間の無駄だ、ここから抜ける」 座り込み、腰に差したスコップを抜いて、砂壁に突き立てる。 「ミニュイもスコップ持ってたよな。足場作って手伝……」 と言いかけたところで、それを遮るように、ミニュイの声が聞こえた。 「感触は、どう?」 「感触?」 ショウは壁の砂を、左手でつかみ取った。 足場のものとは違い、そこはさらさらとした砂になっている。 「意外とあるな……あっさり零れちまった」 言えばミニュイが、どこかでくすりと笑う声がした。 「そりゃあそうよ、巻いてないもの」 「本当巻いていな、……巻く?」 一瞬納得しかけたショウが、おうむ返しに繰り返す。 (巻く? 巻くってなにを、どこに……?) そこまで考え。 「あっ……」 呼吸が止まった。反対に、心臓は一気にどくどく加速する。全身には、じっとり汗が噴き出した。 「ま、まさかっ……」 先ほど、顎でぐりぐりしたものは。 指で感じたむっちりした感触は。 手でつぶしたと思っていたものは。 ショウが、恐る恐る、自身の左手を見やる。 (あれは砂じゃなくてっ……) 「うわああっ!」 ショウは四つん這いで、その場から穴の壁際へと移動した。 手のひらにまた柔らかなものが触れた気がするが、それはあえて無視をする。 だってしかたないのだ、そうしなければ、動けなかったのだから! 砂が落ちてくるのもかまわずに、壁に背をつけ、暗闇に目を凝らす。 ――と、先ほどショウ自身がいた辺りで、もぞりと何かが動く気配がした。 ここに落ちたのは、ショウとミニュイの二人きり。 野生動物が住むような、広い場所でもない、ということは――。 「ふう、やっとどいたわね」 ゆっくりと体を起こしたミニュイは、ショウの額に、手を押し当てた。 「すごい汗……。そんなに驚いた?」 「あ、あれって、もしかしてっ、ミニュイの、む、むっ」 困惑からか、羞恥からか。先を言えぬ男の汗を、ミニュイがそっと、ハンカチで拭う。 「……そうね、たしかにあったわよねぇ? ミニュイの――」 あえてそこで言葉を止めたのは、ショウがごくりと喉を鳴らしたからだ。 「さっきあんなに強く握ってきたのに」 ふふ、と微笑を込めて言えば、ショウがぱっとそっぽを向く。 そして、すねたような、照れたような小さな声が。 「……やめろ」 「巻いてなかったものねぇ?」 にやりと笑って、ミニュイはさらに、口にした。 「やめろーっ!」 ショウが叫び、壁にスコップを突き立てる。 「もう触ったんだから、今更照れてもしかたないわよ」 ミニュイはそんな彼を見、くすくすと笑い声を立てたのだった。 ●存在は必然、接触は偶然 「アユカさんっ!」 花咲・楓の腕が、アユカ・セイロウに伸びる。 だが、アユカが見たのは、そこまで。 突如体を包んだ浮遊感が恐ろしく、目を閉じたからだ。 だからその瞳を開いてすぐ、眼前に楓の顔が見えたときは、驚いた。 「か、かーくんっ!?」 ぺったりくっついた頬を離すも、開いた距離は、吐息がわかるほど。 でも、それ以上は動けなかった。楓の腕が、アユカのウエストに、しっかり巻きついていたのである。 「えっ、ここはどこなの!? なんでこんなことになってるの!? かーくん、大丈夫? かーくん!」 呼んでも返事をしない楓の姿に、アユカの目頭が、どんどん熱くなっていく。 至近距離なのに、暗くて表情がほとんどわからない。それも彼女のパニックを助長していた。 「ア、ユカさん」 楓は、かすれた声を出した。 胸の上にはアユカの体――は、それでいい。落ちるとき、楓はとっさに、アユカを抱きしめた。万が一にも怪我などしないために。 だが、そうして守ったにもかかわらず、名を呼ぶ声が、震えているのはどうしたことか。 「私は、大丈夫ですから……」 そう言って、腕の中にいるアユカの背を、そうっと撫ぜる。 「……よかった……」 アユカが、ほうっと息を吐いた。 と同時に、じわじわと顔に熱が集まってくる。 それはたとえば、自身の丸い胸の下にある硬い胸板や、重なった太腿の太さ、背をなぜる手の大きさを、意識したからだ。 (かーくんって……こんなにちゃんと、男の人だったんだ……) 普段、共にいる彼のことを、異性として意識したことはない。 しいて言えば、アユカの中で彼は『花咲・楓』という存在であり、男でも女でもなかった。 それが、今は――。 (こんなときに、こんなことを考えるなんて、わたしっ……) いったん気にしてしまうと落ち着かず、アユカはもぞもぞと体を動かした。 「あ、あの、かーくん、離して……」 自分を守ってくれた相手に申し訳ないと思いつつ、アユカがそう口にする。 「あっ……すみません、気づかず」 楓はアユカから、ぱっと手を離した。 すぐに起き上がったアユカが、周囲と上を見る。 「ここは……」 「落とし穴の中、ですね」 楓は、砂の上に体を起こした。 周りは砂の壁、見上げる空は丸く切り取られたようとあれば、けして浅い穴ではないだろう。 だが、それはあえて伝える言葉ではない。 「……まあ、出る手立てはあるでしょう」 アユカを安心させるため、とりあえずはそれだけ口にする。 「あ、あるんだ……よかった」 彼女は胸に手を当て、深く息を吐いた。 それを見、楓はすっと目を細める。 (穴に落ちたとはいえ……この反応は大げさすぎないか?) 「そういえば……先ほどはいつになく慌てて、どうしたのですか?」 聞かれアユカは、きょとりと視線を動かした。 「アユカさん? 深呼吸でもして、落ち着いてください」 「う、うん……」 言われるまま、深い呼吸を繰り返す。 「……ごめんね、取り乱して……。言ったら呆れない?」 「……なにを、ですか?」 楓が真顔で問い返してきた。アユカが考えていることなど、まったく思いつかないのだろう。 こうなると、余計に言うのが恥ずかしい。でも真剣そのものの楓の前で、口を閉ざしたままにすることはできず、アユカは思い切って、唇を動かした。 「その、落ちた拍子にいろいろ触ったり触られたりしてないかな、って……」 「えっ……」 絶句する楓の前で、アユカが勢いよく、頭を下げる。 「ああ、やっぱり! 気にしすぎだよね、ごめんなさい!」 「……いえ」 短く返しつつも、楓の心臓は、どくどくと激しく脈打っていた。 アユカの体をそういう気持ちで触ったつもりは一切ない。 ないが、アユカは明らかに照れている。 (俺は……なにかいけないことをしたのか?) 穴に落ちる彼女を抱きよせ、抱きしめ、胸に受け止めた。 ただただ必死で、なにも感じる余裕などなかったけれど。 (……そういえば、柔らかかった気がする……いやいや、何を考えている俺!) 黙り込んだ楓を前に、アユカはほとんど、泣きそうになっていた。 (かーくんは、真剣にわたしを助けてくれたのに、わたしが変なこと言ったからだよね! どうしようっ……) 「かーくん、あの……」 もう一度、謝ってみよう。そう思い、口を開いたところで、楓がぽつりと。 「もしかしてその……妙な所に触れてしまったでしょうか。だとしたら、なんと詫びればいいか……」 およそ彼らしくない小さく弱気な声に、アユカはぶんぶんと首を振った。 「だ、大丈夫、たぶん触られてないし! だから、気にしないで……!」 消えゆく語尾が、楓の不安をかきたてる。 だが、これ以上語れば気まずいのは、二人共だろう。 「す、すみません……」 「ううん、こ、こちらこそ……」 アユカと楓。互いに、砂の壁を見つめつつ。 狭さゆえ触れる背中から、ぬくもりだけは、伝わっていた。 ●黒猫に捧げる純愛 「え、なに? 落ちた……?」 イザベル・デューは、うつ伏せの姿勢のまま、左右を見回した。 周囲は暗く、視界はほとんどゼロ状態。 ただ足の先が壁に触れていることから、ここがひどく狭い場所だというのはわかった。 「……え!? なんで、どうして、いきなり……?」 星と月が出ているとはいえ、それ以外の明かりはなかった海岸沿い。 いや、空の瞬きがあったからこそ、見とれて足元が、おろそかになった。 「どこも痛いところがないのが、不幸中の幸いね……」 そう呟いたところで。 「うぅ……」 体の下から、うめき声が聞こえた。 「あっ、セシルくんそこ!? ごめんなさい、大丈夫!?」 イザベルは、半身を起こした。が、その手のひらが置かれた場所は、セシルの肋骨の上だ。 「大丈夫じゃない、です……」 押さえつけられる圧迫感に眉根を寄せ、セシルは細い声を出した。 「おも……くはないんですけど、ちょっと体浮かせられませんか? 息が……」 正直に言えば、イザベルの体に、肺も気道もつぶれそう。が、重いというのはさすがにまずい。そう考え、言葉を変えたのだが。 「……今、重いって言いかけなかった?」 イザベルは、セシルの上からどきながら、しっかりそんなことを言ってきた。 「そ、んなことはっ……」 セシルが、かすれた声を出す その小さな語尾は、どうやらイザベルの庇護心を刺激したらしい。 「ま、まあ今は追及している場合じゃないわよね」 彼女はそう言って、ふわり、腕に力を入れて、自らの体を持ち上げた。 イザベルは、セシルの顔の横、すなわち砂地に手をおいている。セシルをまたいで開いた膝にも、しっかり力を入れて、彼に体重がかからないようにしていた。 その姿勢で、首だけまげて、上を見る。 「これ、落とし穴よね?」 「まじですか。なんでこんな所に……?」 「それはわからないけど……」 イザベルは、腕の間に仰向けになっているセシルに、目をやった。 「……怪我とかしてないわよね?」 「はい、痛いところはないです」 「……なら一安心、だけど」 そう言って、もう一度、空を切り取っている穴の入口を見上げる。 「私達だけで出るのは難しそうかしら……」 イザベルのダークレッドの髪や、黒い耳は闇に溶けていた。 が、金色の瞳は、はっきりその在処を主張している。 そして、セシルの顔の横で震えている、腕もまた。 「なんか俺が下にいてすみません」 仰向けで寝ているだけのセシルに対し、自らの体重を腕と膝で支えているイザベルは、かなりつらい姿勢だろう。 思い言えば、イザベルは「気にしないで」と頭を振った。 「私もさっき思いきりのしかかっちゃったし」 「ここでよりかかってもいいとか言えたらいいんですけど……、俺の筋力とかだと、とても言えないです」 イザベルが、まじまじとセシルを見つめる。 (……筋力の問題なのかしら。密着しちゃうとか、もっと気にするべき所があるような気がするけれど) だが、水着を着た時も無反応だったから、こんなものかもしれない。 (……とくに、セシルくんの場合は。……そうよ、彼ならきっと) 「そこで提案があるんですが」 セシルは、イザベルの震える腕を横目に、先を続けた。 「……ちょっと予想がついてる」 頭上から聞こえたイザベルの声に、うっ、と息を飲む。 でもだめだ、ここで弱気になったら、望みはかなわない。 セシルは思い切って、口を開いた。 「イザベルさんが猫になれば全部の問題が解決するのでは」 「全部じゃないわね、一部ね」 イザベルはあっさり言い切り、細く息を吐いた。 (本当に隙あらば要求してくるわね……) 年頃の男女が密着することに抵抗を覚えずに、猫の姿を望むとはどういうことか。 一度突っ込みたい気はする。 だが。 「だめですか……?」 セシルの弱気な声が、耳に届くと、イザベルはもう一度、嘆息した。 (まあ今回は理由が正当だし……私も、この姿勢厳しいし) 猫になれば省スペースで、辛い体勢を取り続ける必要はなくなる。そうなれば、体力の消耗も少なくなるし、セシルにとっても、イザベルにとっても、悪いことはひとつもないのだ。 となれば、答えはひとつ。 ※ 「あー、俺ずっとここにいたい……」 つやつやの毛並み、黒猫姿のイザベルが、セシルの腕の中で、もぞりと動いた。 その目は明らかに、何を言っているのかと問いかけている気がする。 が、この優しい体温と滑らかな手触り、なにより愛らしい姿は、セシルにとって、癒し以外の何物でもない。 「もう手放したくない……」 その言葉は無意識。 笑顔もまた、感情が発露しただけの、自然の表情。 だからこそ。 (……気持ちはわかるけど……どういうことよ) イザベルは複雑な気持ちで、セシルを見上げた。 それすら「かわいいです……!」と言われてしまうのだけれども。 ●その手が触れるのはなんのため 「落ちましたカ……」 「落ちましたね……」 エリィ・ブロッサムとレイ・アクトリスは、そろって頭上を見上げた。 砂浜で見ていた星空の一部が、丸く切り取られて視界に映る。 落ちるエリィを抱きとめたまま、レイは砂地に背をつけている。 つまりエリィは、レイの腕の中。 その状態で、レイはエリィに問いかけた。 「怪我はありませんか、レディ?」 「ハイ、レイさんが庇ってくれたので平気デス」 けして無理をしている風ではない、いつもどおりのエリィの声に、レイが安堵する。 しかし、彼女の次の発言には、思わず苦笑した。 「ワタシ、夜の海が危険だと言っていた意味がよく分かりまシタ」 「こういう事態を指したわけではないのですが……」 「エ、そうなのですカ?」 エリィがこてりと首を傾げる。 まるで童女のような仕種に、レイの唇はほころびそうになった。 が、いつまでもこうして彼女をのせたまま、寝転がっているわけにはいくまい。 「とりあえず起き上がりましょうか」 レイはエリィの腰に手を添えようとし――はたと、それをやめた。 無邪気な姿を見せる彼女も、年頃の女性だ。一度断りを入れておいた方がいいだろう。 「あー……少し触れますけど、嫌だったら言ってくださいね」 「ハイ」 エリィはにっこり微笑んだ。 知らぬ男が触れるとあれば、さすがに問題だ。 だが相手が彼であれば。 (レイさん紳士だし、全然平気デス) ――と、思っていた、のだが。 (……えっ?) 彼の大きな手のひらが、レイの細いウエストに、触れる。 たったそれだけのことで、彼女の肩は、ぴくりと跳ねた。 「……レディ?」 動きで動揺が伝わったらしい。心配しているような、レイの声が聞こえた。 「イエ、ナンデモナイデス! 大丈夫デス!!」 エリィはぶんぶんと首を振る。 腰は掴まれているが、指はそこにあるだけ。けして不埒な動きはしていない。 (ソウデス、他意はないのデス。……少しくらい我慢しまショウ) 「ふむ……では続けますよ」 レイはエリィを持ち上げるようにして、自らの太腿の上に座らせた。砂の上に手をつき、上半身を起こす、と。 「あっ……」 エリィの体が、後ろに傾ぐ。その背に手を添え支えると、彼女の薄い筋肉に力が入った。緊張しているのだ。 (レディは僕を意識していないと思っていましたが……。こんな反応を見ると、楽しくなってしまいますね) レイは笑み、再び手のひらを、エリィの腰へと添えた。 その手のひらを、腰骨からウエストへ。肋骨の下の辺りまで、ゆっくり滑らせる。 そして――。 手の十指を、もぞと動かした。 さわさわと蠢く指が、団服の下、エリィの柔らかな肌を刺激する。 「えっ……!? あ……やっぱり待ってくだサイ……そこは!」 反射的に、エリィはレイの手首を掴んだ。が、彼の指の動きは止められず。 「……ふはっ、アハハハハハハ!!!」 いよいよ彼女は、声を上げて笑い出した。 「く、くすぐったいのでっ、ソコは触っちゃダメデスーっ!」 レイの太腿の上に座り、体をよじって、エリィはしばしの間、笑い続けた。 「アハ、ハハハッ、やめて、やめてくだサイッ……!」 ぱたぱたと頭を振って、レイの腕を叩いてくるエリィ。 そんな姿も愛らしいのだが、彼女の声に涙が混じり始めたとき、レイはくすぐる手を止めた。 「すみません、つい楽しくなってしまって」 「うぅ、ひどいデス……笑いすぎて腹筋が痛いデス……」 呼吸を整えながらの涙声に、レイがエリィの顔を覗き込む。 とはいってもここは闇に覆われた穴の底。ごく至近距離まで近づかなければ、表情まではわからない。 「レディ、大丈夫ですか?」 レイがそう尋ねたのは、エリィの鼻先、わずか数センチでのことだ。 ――と。 ふふっと微笑む吐息が、レイの唇にかかった。 「いえ、ただ……レイさんがこんなに楽しそうなのは初めてだったので。嬉しくなってしまいまシタ」 そう言うエリィは、おそらくレイの顔が、そこまで近い位置にあることに、気がついていないだろう。 だがレイには、エリィがへにゃっと笑った顔が、はっきり見えた。 そのうえ、エリィの指摘自体、とても恥ずかしいものだったから。 「え……」 つい一瞬。彼は言葉を失った。 ただ、そのわずかな沈黙に、エリィは気づかない。 彼が、その手でそっと、レディの手を取ったからだ。 「狭いですが……立てますか? レディ。早く出ましょう。そうでないと……また触れたくなってしまいますから」 「えっまだくすぐる気デスカ?! 勘弁してくだサイ!」 エリィは慌てて、腰を持ち上げようとする。 その頭に、レイの手のひらがのった。 「いえ、こういうことですよ」 「頭に触りたいんデスカ?」 エリィが、きょとりと首を傾げる。 (レイさんって、よくわからない人デスネ……) ただ、その手は優しく心地よくて。 エリィはうっとりと目を閉じた。胸の奥のざわつきは、少女にはまだ、わからない。
|
||||||||

|

|

|
||||||
|
*** 活躍者 *** |
|



























