| アブソリュートスペル(魔術真名) |
|
|
|
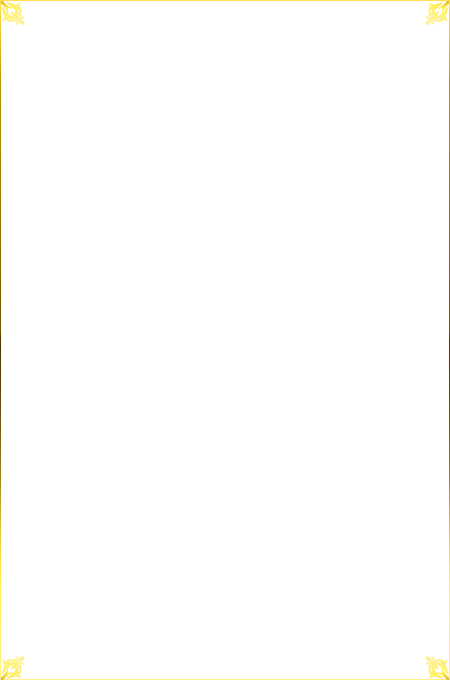
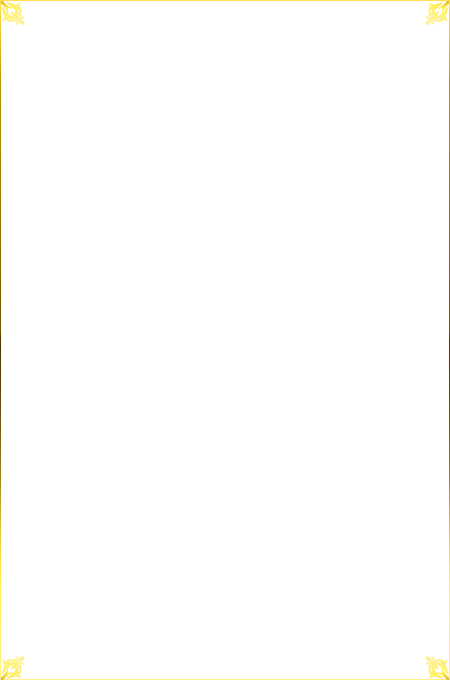

プロフィール
| 名前 | ディルク・ベヘタシオン |
| 呼び名 | シエラ |
| 種族 | 人間 |
| アライブ | 悪魔祓い |
| 血液型 / 属性 | A / 火 |
| 性別 | 男性 |
| 誕生日 | 1月1日 |
| 外見年齢 | 32歳 |
| 実年齢 | 外見相応 |
| 身長 | やや高い |
| スタイル | 普通 |
| 利き手 | 右利き |
| 髪の色 | 赤茶 |
| 瞳の色 | 【左】青 【右】青 |
| 肌の色 | 色白 |
| 性格 | 乱暴 |
| 一人称 | 俺 |
| 二人称 | お前さん |
| 口調 | ~だろ、~だぜ |
| 敬語 | 使わない |

ステータス
| HP(体力) | 63 / 63 |
| MP(魔力) | 52 / 52 |
| 攻撃力 | 20 + 10 |
| 魔力攻撃 | 17 + 0 |
| 防御力 | 17 + 1 |
| 魔力防御 | 15 + 0 |
| 速力 | 1 + 0 |
| 命中力 | 18 + -12 |
| 回避力 | 14 + 0 |
| 抵抗力 | 14 + 0 |
| 運命力 | 10 + 2 |

スペック
| STR(筋力) | 11 + 0 |
| INT(知力) | 9 + 0 |
| VIT(頑丈) | 8 + 0 |
| MND(精神) | 7 + 0 |
| DEX(器用) | 10 + 0 |
| AGL(敏捷) | 6 + 0 |
| CHR(魅力) | 9 + 0 |
| DES(運) | 6 + 0 |

ベリアルやヨハネの使徒に大切な人を殺されたため

α. 正義執行 ( 60 )

傍から見れば、彼は『復讐者』に見えるだろう。
孤児院を営む夫妻の子どもとして生まれ育ち、彼が12歳の時に孤児院がベリアルに襲撃された。
その際に彼一人だけが逃げ延びて唯一の生存者となり、それ以来ベリアルを狩る為に活動している。
復讐者としてはありがちな生い立ちだが、彼が真に憎悪するのはベリアルやヨハネの使徒ではない。
『慢心』
彼の育った孤児院は郊外でありながら、比較的教会の目の届きやすい立地にあった。
にもかかわらずベリアルの襲撃を許したのは、その状況に慢心して警戒を怠った、教会と孤児院双方の「この状況で襲われるはずがない」という慢心の結果である。
「この世界に『当たり前の安全』なんてものは存在しねぇ。そんなものを信じて縋るクズは、例外なく皆くたばるべきだろう」
ベリアルの襲撃に気付き両親に知らせるも、それを信用されず一人で逃げ出した少年。
生き延びたが故に、彼は歪んだ。
仇であるベリアルに真っ直ぐに憎悪を向けられていれば、どれだけ幸せだっただろう。
だが、彼が憎んだのは『慢心』という感情。
自分は強いから安全? ならば死ね。
自分は守られているから安全? ならば死ね。
もう敵は倒したから安全? ならば死ね。
人も、ベリアルも、ヨハネの使徒も、慢心することは許されない。
ありとあらゆる慢心という罪に死の制裁を。
その信念の下、彼は今日も銃を手に取る……。

プロフィール
| 名前 | シエラ・エステス |
| 呼び名 | ディルクさん |
| 種族 | 人間 |
| アライブ | 断罪者 |
| 血液型 / 属性 | 不明 / 陰 |
| 性別 | 女性 |
| 誕生日 | 6月26日 |
| 外見年齢 | 20歳 |
| 実年齢 | 自分でもわからない |
| 身長 | 普通 |
| スタイル | 細身 |
| 利き手 | 右利き |
| 髪の色 | 漆黒 |
| 瞳の色 | 【左】黒 【右】黒 |
| 肌の色 | 日本人肌 |
| 性格 | 弱気 |
| 一人称 | 私 |
| 二人称 | あなた |
| 口調 | ~です、~ですね |
| 敬語 | 使う |

ステータス
| HP(体力) | 63 / 63 |
| MP(魔力) | 25 / 25 |
| 攻撃力 | 20 + 14 |
| 魔力攻撃 | 20 + 0 |
| 防御力 | 17 + -2 |
| 魔力防御 | 20 + 0 |
| 速力 | 1 + 0 |
| 命中力 | 13 + 0 |
| 回避力 | 19 + 8 |
| 抵抗力 | 14 + 0 |
| 運命力 | 5 + 1 |

スペック
| STR(筋力) | 11 + 0 |
| INT(知力) | 10 + 0 |
| VIT(頑丈) | 8 + 0 |
| MND(精神) | 10 + 0 |
| DEX(器用) | 7 + 0 |
| AGL(敏捷) | 9 + 0 |
| CHR(魅力) | 11 + 0 |
| DES(運) | 5 + 0 |

成り行きに任せたらいつのまにかエクソシストになっていたため

α. 自己防衛 ( 54 )

彼女には何も無かった。
幼い頃の記憶は朧気で、親の顔は知らない。気が付けばスラム街を徘徊しており、エクソシストの素質を持つとして教団に保護された。
そんな彼女が教団の庇護下にあって感じたのは『劣等感』だった。
自分は、なんと場違いな存在だろう。
多少の教養を身につけたくらいでは歩み寄ることもできない程に、自分は劣った存在だ。
それ故に、彼女は自らに向けられたあらゆる虐待や差別に対して抵抗をしなかった。
そんな権利など自分にはない。
こういった『捌け口』となることが自分のこの場所での役割なのだろうと考え、全てを受け入れていた。
……自分を虐待していた男の頭が、目の前で弾けるまでは。
恐怖を感じた。
極めて個人的な思想の下に、教団の関係者を何の躊躇いもなく射殺したエクソシスト。
彼の狂気を前に、これまでにないほどに『死』を身近に感じた。
名誉も立場も、貞操すら守ろうとしていなかった彼女は、その恐怖を前に変わった。
自分の身は自分で守らなければならないと、最低限の自衛をするようになったのだ。
どれだけ白い目で見られようと、どれだけ恥をかこうと平気だが……死ぬのだけは、恐い。
特にあの狂人に殺されるのは、絶対に避けたい。
その思いの下に彼女は生き方を改め、力をつけていくのだが……。
……やがてその狂人が自らのパートナーになると知り、彼女は白目を向いて昏倒した。


